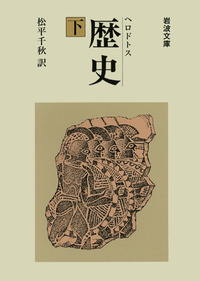政治書を列挙します。
中国では、儒家の四書五経。司馬遷の史記。ギリシャでは、プラトンの国家論。ヘロドトスの歴史。ローマ帝国ではカエサルのガリア戦記。マルクス=アウレリウスの自省録。日本では、古事記と増鏡。中世ヨーロッパでは、マキャベッリの君主論。ウィクリフの領主論。などなどがあります。
そこから、近代に入ると啓蒙思想、財政学、経済学、資本主義とその批判など領域があまりに多岐に渡って追いきれません。
政治書が難しいのは、一時的にせよ勝利者となった人のものしか残らないということです。
そこの辺りにある共有意識が分からない側にいる自分としては、まあ、評価は難しいなあという感じです。
そこで読んだことのある政治書の雑感を書いていこうかなあと思います。
プラトンの国家論。
いわずと知れた倫理の教科書に出てくるあの人です。
哲人政治を唱え、民衆を哲人独裁によって支配する、という内容です。古代ギリシャの分裂したポリス政治からは、シラクサの独裁が羨望的に見えていたらしいです。シラクサには後にアルキメデスが生まれるわけですから、プラトンの羨望した独裁もそう酷いものではなかったのでしょう。
犬に誓って。というdog→godという遊びがギリシャ文明の担い手の自負を表しているのでしょう。不敬ですが。
次、ヘロドトスの歴史。
オリエントとギリシャ世界の歴史を包括的に描いた歴史学のパイオニア的作品です。
ペルシアの勃興とリディア、メディア、ヒッタイトを含んだオリエントの動乱と、ギリシャの賢人ソロンに見える民主社会の理想の投射と、イオニアのクロイソス王の栄華と衰退を通して見えるムーサの糸の残酷さが骨太な史実に深みを与えています。
マラトン、テルモピュレー、サラミスと続く戦争とギリシャの栄光には感動を覚える。
クセルクセス一世の無敵のペルシャ軍への信頼とヘロドトスが歴史的結果を知った上で描く、王の感嘆には心が動かされる。
政治書としてみると、ギリシャのポリス政治の正統性と、神託の読み違えに対する巫女の即妙な返答、スパルタ、アテネの二大国家の理想と現実政治の奇々怪々、そして、都市が国家なのではなく、市民が国家なのだという強いアテネの叫びに現代市民としては感動を覚えずにはいられない。また、ペルシャ王国の洞察も素晴らしい。
次、ガリア戦記。
カエサルの戦争記。ローマ軍はとにかく強い。補給、工兵など、ローマが世界帝国になれた軍備がよくわかる。
うーん。私、言うほど読んでいないなあ。
古代ギリシャの政治書は民主政体だったから、今でも読むと深い理解が得られるのかも。
啓蒙思想では、ルソーの人間不平等起源論や、ロックの市民政府二論、ミルの自由論などは手に取ったことがあるのですが、これはまた次の機会に書けたら書けます。
梶井基次郎が言っていますが、桜の木の下には死体が眠っているのです。
美しい成功談や、文化の華は死屍累々の屍の上に咲くあだ花のようなものなのかもしれません。
政治書を読んで、古代の賢哲や王者の風に触れてみるのも、現実の逃避としては良いものですね。