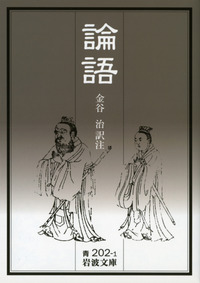知ら知るなかれ。寄らしむべし。
孔子はそう言ったそうです。
私の家は武士ではないので、〇〇源氏とか、〇〇平氏とかの血が流れている可能性はほぼゼロなのですが、日本では何割かが、確実に父系の天皇家の血を引く武士であり、その繋がりを見ていくとほぼどこかの武家の血の帰属下にあるのでしょう。
天皇家が大和王権を確立した5世紀の時点で、天皇家の血脈が100人を超えていたなら、その後、100年で、20年ごとに2倍に増えてゆくとするなら、2の5乗で3200人まで増え、その後の100年で102,400、その後100年で3,276,800となります。白村江の戦いに十数万を動員できたのも肯けますね。
それ以降、日本の律令制度の限界が来て破綻するまでは微増が続き、それ以降は農業生産性の向上に伴って微増していったのででしょう。
ところで父系だけが天皇家の子孫を名乗れる現状からすると、100人から20年で1.2倍ずつ増えていったとすると、1800年で34,888,895という数字が導け、日本人のほとんどは天皇家の父系の子孫を持つという計算結果になります。
調べてみると、あなたも、天皇家の家系の一員かも。
さて、ところで300年で家系は約32,000倍に増えるわけですが、中国の歴史でもおそらくそうだったのでしょう。孔子の生きた春秋戦国時代には、殷の末裔の宋、太公望の末裔の斉、南方の大国楚、呉、越、そして統一者の秦を除くとほぼ周王室の子孫という意識を持った家系ばかりだったのでしょう。
その現実が、結局、春秋の覇者斉の没落をもたらし、秦の統一後の混乱を引き起こし、劉邦をして項羽に破れさせたのでしょう。
そのような状況下で、魯の宰相を務めた、儒教の創始者孔子は知ら知るなかれ、寄らしむべしと唱えました。
おそらく、身分制の帰属意識を捨て去った労働力の確保と、文化の維持のためにそう唱えたのでしょう。
身分等しく、知も等しく、力も等しい。その時代に何を持って支配できるか、という考えが多少はあったのでしょう。
その流れで、法家が現れ、秦の統一が行われたわけですが、その肝心の秦の始皇帝が皇帝という、神に由来した絶対権力の名を選び、そう振る舞ったとき、儒教の勝利が決まったのでしょう。
あのまま、中国で法家の唱えた通りの統治が行われていたら、というのはロマンのあふれるお話ですね。
その後、中国は、科挙の採用により、試験エリートという狭き門の通過者という合理性で支配の正当性を見出したわけです。
知ら知るなかれ、寄らしむべし。
昨今、学歴社会の弊害が唱えられていますが、試験エリートの夢もなくなった時、支配の合理性はどうなるのでしょうか。
私は、経済学の信奉者だから、企業家のアニマルスピリットと資本の相続が支配の合理性であってもよいとは思います。
ですが、まあ、あまり賛同は得られないでしょうね…。
歴史というのは断絶しているようで、意外に連続しているのかもしれません。
あ、そうです。政治に触れるとどうしても血筋の話になってしまいますが、しょせん、人間は猿から進化した黒人のアダムとイブの祖先です。
ルソーが言っている通り、天皇家の血筋が入っていないとしても、我々は、神が創られたアダムとイブの子孫なのです。
胸を張って生きましょう。